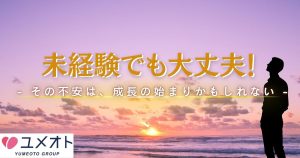経営戦略室のやまもとです。
電話が苦手…という人が増えている

離れた場所にいる相手に伝える手段と言えば電話かメール(ここではチャットやLINE等も含めた総称として使います)が一般的です。
しかし「最近の若い人は電話が苦手」と耳にする機会が増えました。
昔は電話という手段しかありませんでしたが、eメール、そしてLINEなどの便利なアプリが普及した事によって、電話以外の手段がより手軽に、より身近なものとなり電話離れが加速し、さらにはコロナ禍で人と直接会う機会、話をする機会が減った事が原因と言われています。
私は40代ですので言わば電話世代ですが、仕事もプライベートも完全にメール派です。仕事の電話をのぞき、余程タイミングが良くなければ電話には出ません。
しかし私がメール派なのは「電話が苦手」という理由ではありません。ここでは私がメール派である理由について考えたことをまとめました。
電話よりメールを利用する理由

「記録性」「迅速」「効率的」「相手への配慮」これらが私がメールを利用する理由です。以下に説明します。
メールは情報の記録性が高く、後から内容を振り返ることが容易です。特に業務上の重要な指示や進捗報告は、証拠として残す意味でもメールが適しています。
また、事前に内容を整理し、重要なポイントのみを伝えられるため、やり取りがシンプルかつ迅速になります。
上司や部下、同僚など複数の関係者が関与するプロジェクトでの確認や相談も、一斉に情報を共有できるので効率的です。
さらに、メールは相手が都合の良いタイミングで確認をする事ができるという点や、要点を簡潔にまとめて送信することで相手が情報を瞬時に把握できるという点など、相手への配慮が可能です。
電話のメリット、デメリット

電話が完全に不必要というわけではありません。緊急の連絡や、その場での即時の意思決定が求められる場合には電話が最適な手段です。
しかし個人的にはそれ以外のメリットは思いつきません。
電話派の人は良く「電話の方が早い」と言います。それが上司であれば仕方がない事ですが、そうでない限りはその理由は完全に一方的で相手への配慮に欠けていると考えます。配慮というのはコミュニケーションコストをどちらが支払うか、についての配慮です。
電話は、電話を掛ける側よりも電話を受ける側の方がコミュニケーションコストが大きくなってしまう事がデメリットです。
コミュニケーションコストとは

メールを送るという行為には、一度話をまとめて言語化する必要があるため、言葉を選ぶ、整理する、相手の反応を想像する、分かりずらい場合には書き直すなど、コミュニケーションを行う上でエネルギーも時間も使い、実は様々なコストが発生しています。
それらの言語化するためのコストや消費する時間のコストを「コミュニケーションコスト」と呼びます。
大事な内容であったり、文章量が多くなる場合はそれなりに言語化も大変で、時間も必要となり、メールを送る側のコミュニケーションコストは大きくなります。つまりメールは手間ではありますが、メールを送る側がコミュニケーションコストの大部分を負担しているのです。
電話をかけるという行為は、相手も言語化するコストを負担してくれる為、自分ひとりで言語化する必要がなくコミュニケーションコストは比較的小さくて済みます。一方で、情報を整理したりメモを取ったりするのは電話を受ける側となる事が多いため、電話を受ける側のコミュニケーションコストは大きくなります。
電話派の人が「とりあえず電話しよう、その方が早いし楽」と感じるのは、知らず知らずのうちに相手にコミュニケーションコストを支払わせているからなのです。にもかかわらず「相手もその方が楽なはずだ」なんて思っている人も少なくありません。
電話を受ける側が支払うコミュニケーションコスト

電話は業務に集中している時であっても、会議中であっても、突発的に割り込んで来るため、例え電話に応答しなくてもリズムを乱されます。応答した場合はなおさら、他の業務を中断しなければならず、作業や集中を妨げられます。
業務の内容にもよりますが、人が中断された作業に戻り、元の集中状態に戻るのには平均で約23分かかるそうです。このため、重要な作業や思考が必要な業務を行っている際に着信があると、業務の効率を著しく下げ生産性の低下を招く事になります。
さらに、電話でのやり取りは会話の流れで話題が拡散することが多く、結論に至るまでに余分な時間を消費することも少なくありません。
「とりあえず電話してくる人」は話がまとまってないことが往々にしてあるので、話を整理し、より深く聞くために質問する必要があり、多くのエネルギーを消費します。
著名人ではホリエモンやイーロンマスクが電話を嫌う人として有名ですが、彼らが電話を嫌う理由は上記の通りだそうです。
会って話をするのも同じ

ここまでは電話とメールを例にしましたが、直接会って話をする場合も電話と同様です。
例えば上司に何か相談したいことがあった時、緊急でもないのに相手のタイミングを考えず「今ちょっといいですか?」と話しかけていないでしょうか?
優しい上司であれば、自分が支払うコミュニケーションコストの事は考えず対応してくれるでしょう。そうでない上司の場合は機嫌を損ねてしまったり「こいつウザイやつだな」なんて思われてしまう事もあるかもしれません。
私も経験がありますが、突発的に相談をしてくる部下は多くの場合、話がまとまっておらず、自分がどうしたいのかさえ分かっていない事が多いです。
何も考えずに「どうしたらいいですか?」と聞くだけでは、上司に考えてもらっているだけで、自分が考えなくていい状況を作ることになります。あえて厳しい言い方をすれば上司に言語化コストを負担させて責任を転嫁しているとも言えます。
逆に「いついつ相談の時間をください」と言ってくる部下は、自らが言語化コストを負担し、しっかり準備が出来ています。結論が出せなくても、整理するところまでやってから相談に行くだけで相手の負担はぐっと減るのです。
まとめ
ここで一番伝えたかった事は「コミュニケーションのコストをどちらが払っているかを常に意識して欲しい」という事です。
言語化する為のコストを進んで支払う癖を付け、常に相手の立場になった行動が取れると上司や同僚からも一目置かれる存在になるでしょう。